卓球の
歴史
について
卓球のイロハ
卓球の世界へようこそ♪
卓球の歴史について
卓球はあの国で生まれた?!
シェークとペン
どこが違うの?
ラケットの選び方
ラケットはどうやって選ぶ?
ラケットの種類
ラケットの種類って?
ラバーの種類
裏とか表とか?
ラバーの厚み
厚みの違い?
ラバーのお手入れ
寿命があるの?!
ユニフォームについて
公認じゃないとダメ?!
準備運動
ケガしちゃうよ!
卓球の筋肉
ハッスル!
卓球でダイエット
スリムでキレイに!
ラージボール
ラージボール?
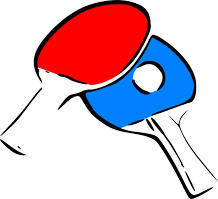
■卓球の起源について
卓球は、19世紀の終わりごろにイギリスで生まれたスポーツです。もともとは、上流階級の人たちが屋外で楽しんでいたテニスを、冬の寒い時期でも室内で楽しめるように工夫したのが始まりです。
当時は、本をネットの代わりに立てたり、ワインのコルクをボールにして遊んだりしていました。ラケットも、紙を巻いたものや簡単な木の板などが使われていたそうです。
やがてこの遊びは人気を集め、1901年には「ピンポン(Ping Pong)」という名前でおもちゃとして商品化されます。この名前は、ボールが台やラケットに当たる音をまねたものでした。
その後、競技としてのルールも整えられ、1926年には「国際卓球連盟(ITTF)」が設立され、世界大会が開かれるようになりました。
日本には明治時代の終わりごろに伝わり、学校や地域で広まっていきました。そして、1988年のソウルオリンピックでは、ついに卓球が正式なオリンピック種目となりました。
■日本ではどのように普及していったの?
卓球は、明治時代の終わりごろに「ピンポン」という名前で日本に伝わりました。当初は上流階級の遊びとして親しまれていましたが、その後、徐々に学校や地域の中に広まっていきます。
大正から昭和初期にかけては、卓球が学校教育やクラブ活動に取り入れられるようになり、特に中学・高校・大学などの部活動を通じて若者の間に普及していきました。
室内で気軽にできるスポーツであることから、多くの学校で採用され、人気が高まっていきました。
昭和6年(1931年)には「日本卓球協会」が設立され、全国規模での大会開催やルール整備が進められ、競技としての基盤が整います。
戦後になると、日本の卓球は世界でも注目される存在になります。1952年には荻村伊智朗選手が世界選手権で優勝し、国際舞台での活躍が日本中の注目を集めました。
この活躍をきっかけに、卓球は国民的なスポーツへと成長していきます。
その後も、福原愛選手や張本智和選手などのスター選手が登場し、テレビやメディアを通じて幅広い世代に卓球が親しまれるようになりました。
さらに、現在では「Tリーグ」というプロリーグも発足し、競技としてだけでなく観戦スポーツとしても人気が高まっています。
このように、卓球は100年以上の時間をかけて、日本の社会や文化に深く根づいてきたスポーツなのです。